
成年後見制度の利用が広がるにつれ、後見人が被後見人(成年被後見人)の逝去後に遺品整理を行うケースが増加しています。
しかし、後見人の職務範囲には、本来「遺品整理」そのものは含まれておらず、法的な手続きや対応には細心の注意が求められます。
「後見人として、どこまで遺品整理に関与すべきなのか?」 「財産管理と遺品整理の線引きはどこにあるのか?」
このような疑問を抱える後見人の方々は少なくありません。この記事では、後見人が遺品整理を行う際の法的な手続きと、実務における流れなどをご紹介します。
成年後見制度は、判断能力が不十分な方の財産管理や身上監護を支援する制度であり、遺品整理は相続人が行うべき行為とされています。
しかし、実際には、相続人が遠方に住んでいたり、相続人同士の意見が対立したりするなど、様々な事情から後見人が遺品整理をせざるを得ない状況も発生します。
そのような状況において、後見人はどこまで遺品整理に関与できるのでしょうか?また、どのような点に注意すべきなのでしょうか?
後見人の皆様が、安心して遺品整理を行えるよう、この記事では、後見人が遺品整理を行う際の法的な手続きと、実務における流れなどをご紹介します。
1. 後見人が行うべき業務と遺品整理の関係
まず、成年後見制度における 後見人の役割と業務範囲 を確認しましょう。

成年後見人の役割
後見人は、判断能力が低下した被後見人に代わって、
しかし、後見人の業務は「被後見人が生存している間」 に限定されます。
後見人の業務範囲
【 可能な業務】
• 被後見人の財産管理(預貯金の管理、不動産の処分など)
• 生活・医療・福祉に関する契約の締結(

【 できない業務(被後見人の死亡後)】
• 遺品整理(遺産の処分)
• 相続手続き
• 遺言執行
つまり、後見人が直接遺品整理を行うことはできません。
しかし、後見人には「相続人へ財産を引き継ぐ責務」がある ため、死亡後に一定の手続きが求められます。
2. 後見人が死亡後に行うべき法的手続き
被後見人が死亡すると、後見人の役割は終了します。
しかし、後見人には「最終業務」としてやるべきこと があります。

① 家庭裁判所への報告
後見人は、被後見人が死亡したら 速やかに家庭裁判所へ報告 しなければなりません。
【 報告に必要な書類】
• 被後見人の死亡届
• これまでの財産管理の報告書
• 残存財産の明細(預貯金、現金、不動産など)
家庭裁判所への報告を終えると、後見人の役割は正式に終了 します。
② 残存財産の引き継ぎ
後見人は、被後見人の財産を相続人や遺言執行者へ引き継ぐ 必要があります。
◆相続人の調査
• 戸籍謄本を取得し、法定相続人を特定する。
◆財産の引き継ぎ手続き
• 預貯金、不動産、有価証券などの資産を相続人へ引き渡す。
◆相続人不在の場合
• 相続人がいない場合は、家庭裁判所に「相続財産管理人」
ここで注意すべき点は、
財産は相続人のものになるため、
3. 遺品整理が必要な場合の対応方法
後見人が直接遺品整理を行うことはできませんが、
① 相続人がいる場合
後見人は、財産の一覧を作成し、相続人へ情報提供 することで、遺品整理をスムーズに進められます。
【 遺品整理の進め方】
• 相続人へ財産リストを渡す
• 遺品整理業者を紹介する
• 遺品の処分について相続人の意向を確認する
相続人が決まっている場合は、基本的に 遺品整理の判断は相続人に委ねる ことが重要です。

② 相続人がいない場合
相続人がいない場合、財産は最終的に 国庫へ帰属 します。
この場合、遺品整理は 「相続財産管理人」 が対応することになります。
【 後見人の対応】
• 家庭裁判所へ相続財産管理人の選任を申し立てる
• 相続財産管理人が遺品整理を行うまで財産を保全する
• 現金・貴重品などの保管場所を整理しておく
このように、後見人は 遺品整理の主体ではなく、手続きのサポート役 となることが求められます。
4. 遺品整理業者との連携
成年後見人が遺品整理を行う際、直接的な作業が困難な場合や、専門的な知識・技術が必要な場面では、遺品整理業者との連携が不可欠です。
遺品整理業者は、単なる不用品処分だけでなく、遺品整理に関する様々なサービスを提供しており、後見人の業務を円滑に進める上で強力なパートナーとなります。

遺品整理業者が提供する主なサービス
- 遺品の仕分け・整理:
- 膨大な量の遺品を、貴重品、思い出の品、処分品などに丁寧に仕分けします。
- 故人の生活状況や価値観を尊重し、遺族の気持ちに寄り添った作業を行います。
- 不用品の処分・リサイクル:
- 法令に基づき、適切な方法で不用品を処分します。
- リサイクル可能なものは、専門業者に引き渡し、環境に配慮した処理を行います。
- 重要書類や貴重品の捜索:
- 遺言書、権利書、通帳、印鑑など、重要な書類や貴重品を徹底的に捜索します。
- 専門的な知識と経験に基づき、隠れた場所にある貴重品も見つけ出します。
- 空き家の清掃・管理:
- 遺品整理後の空き家を、清掃、消毒、簡単な修繕などにより、適切な状態に保ちます。
- 定期的な訪問や管理を行い、空き家の劣化や犯罪を防止します。
- 特殊清掃:
- 孤独死や事故現場などの特殊な清掃にも対応できる業者もいます。
遺品整理業者との連携における後見人の役割
- 遺品整理業者の選定:
- 複数の業者から見積もりを取り、サービス内容、料金、実績などを比較検討します。
- 信頼できる業者を選定するために、口コミや評判も参考にしましょう。
- 相続人との連携:
- 遺品整理の進め方や処分する遺品について、相続人の意向を十分に確認します。
- 相続人との合意形成を図り、トラブルを未然に防ぎます。
- 遺品整理の監督:
- 遺品整理業者に丸投げするのではなく、作業の進捗状況を適宜確認します。
- 重要な遺品の取り扱いなど、注意すべき点は業者に明確に伝えます。
- 遺品整理後の報告:
- 遺品整理の作業内容や処分した遺品について、詳細な報告書を作成し、相続人に提出します。
- 金銭の動きがあった場合、その明細も明確にします。
特に、相続人が遠方に居住している場合や、高齢で遺品整理が困難な場合には、遺品整理業者の専門的なサービスが非常に有効です。
後見人は、遺品整理業者との適切な連携を通じて、被後見人の遺品整理を円滑に進め、相続人の負担を軽減することができます。
後見人が直接遺品整理を行えない場合でも、
5. まとめ:後見人が遺品整理に関わる際の注意点
成年後見人は、被後見人の生前の財産管理を行いますが、
しかし、被後見人の死亡後に行うべき業務として、
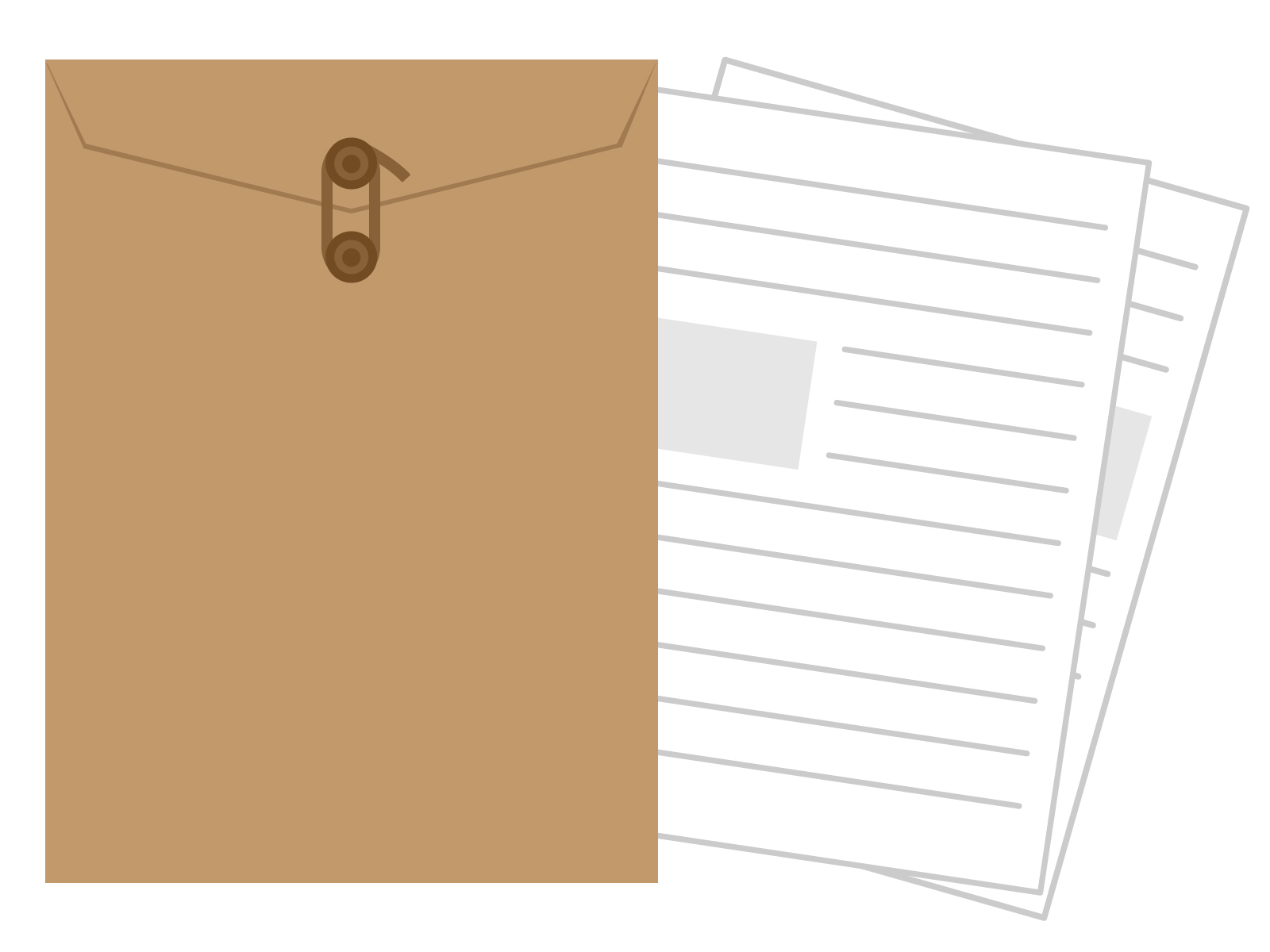
【 後見人がやるべきこと】
● 家庭裁判所へ報告する
● 財産を相続人または相続財産管理人へ引き継ぐ
● 遺品整理の業者を紹介し、相続人の負担を軽減する
【 後見人がやってはいけないこと】
● 勝手に遺品を処分する
● 遺品を売却して現金化する
● 相続人の意向を無視して遺品整理を進める
成年後見制度の運用が増える中で、
適切な法的手続きを踏み、相続人や専門家と連携することで、


